Archive for the ‘(連載)たそがれ駄小説’ Category
連載⑬: 『じねん 傘寿の祭り』 一、 チヂミ (9)
一、 チヂミ ⑨
裕一郎は、その後高志と当然仕事で何度も顔を合わせたが、亜希のことには触れていない。介入はまるで自身の家庭崩壊を辿るようなことでしかないと思ったし、何よりも、高志が亜希に心奪われた理由がよく解かったからだ。 一週間後、亜希は仕掛りの現場を後輩へ丁寧に引継ぎ、一身上の事情によりと告げて退社して行った。余りの素早さに驚いたが、高志が自らスパッと身を処さない経過に先行きを確信したのか、高志とのしたくも無い駆け引き、妻とのドロ試合など「キャリア」にならないと考えたのか…。 裕一郎は、その行動をアッパレと思った。もちろん裕一郎には何の連絡もなかった。 元居たNGO団体に戻ったとか、沖縄に向かったとか噂されたが、亜希の交友関係は社内の誰も知らず、年が明けた頃にはもう亜希の話題は出なかった。
 黒川からの誘いを何度も受け沖縄へ行こうかと思い始めていた。拾ってもらいながら三年にも届かず去ることははばかられたが、三月末とうとうノザキの野崎氏に願い出た。それを伝え聞いた高志は一応慰留したが、それは形式的なものだった。 一女性社員の退社が、例え自身との私的な関係に由来しているとしても、それが裕一郎が職場を去る理由に重なると、高志が考えるのは奇妙ではある。裕一郎が、自分の撤退と亜希のことが関連しているだろうなと自覚するのも同様だ。 何故だろう。その奇妙をむしろ当然だと思ってしまう六十近い男が二人、若い娘が遺して行ったある鮮やかさに支配されて向かい合っていた。 「秋に松下君が辞める前、逢うたんか? 何か言うてたか?」 「いや。現場帰りに呑んだけど何も言うてなかったぞ。なんで?」 「そうか。そんな気がしたんや」 高志のデスクと社員のデスク群との間の壁面に、コルクボードがあって、様々な連絡事項が貼られている。資格試験の講習会、新入社員歓迎会・・・。隅に絵葉書がピン止めされている。松下さんより!と矢印を描いた紙が横に貼ってあった。 「見てもええかな?」 「ああ・・・。辞めた直後、チーム宛に来たらしい。何ヶ月にもなるのに、連中が外し忘れとるんや。瀬戸内海の写真やな、消印は下関や。携帯電話の番号もアドレスも変わっていて繋がらないらしい」 手に取って、絵写真の裏を見ると、宛名欄の下半分にチーム員四人のニックネームがあって、その一人一人への短い激励とアドバイスが書いてある。寝過しが貴方のホントの力量を半減させていると思う、現場に足を運べば今以上に人は動いてくれるはず、発注遅れは結果としてと言う以前に元々現場軽視なんです、連日事務所に遅くまで残っているのは決して誇るべきことではありません、などとあって、最後の行にこうあった。 私? 『ひと夜秘め独り往く朝霧あさし身捨つるほどの恋路はありや』 高志が「そんな気がしたんや」と言った根拠は分かっていたが、答えようもない。 「松下さん、誰かと別れたんか?」 「心当たりないな・・・。社員のプライベートは知らん」 「パロディと言うか、これ本歌取りやな。本歌作者は笑うてるやろうけど、これは相手を責めるというのではなく、精一杯、自分と相手両方と言うか、関係全体を相対化しようと真面目に振り返っているよな」 「・・・・・・」 「高志。得難い人が辞めたな」 「・・・・・・・。黒川さんを手伝うって? 二度ほど彼から焼物を買うたことがある。大変やぞ、あのジジイ」 「ああ分かってる。まぁ短期間やし、沖縄には迷惑やろうが、癒し?リフレッシュ?」 「裕一郎、大阪に帰ったら、戻って来てもええんやぞ。場所は用意する」 声を出さず、片頬だけ崩して返した。
黒川からの誘いを何度も受け沖縄へ行こうかと思い始めていた。拾ってもらいながら三年にも届かず去ることははばかられたが、三月末とうとうノザキの野崎氏に願い出た。それを伝え聞いた高志は一応慰留したが、それは形式的なものだった。 一女性社員の退社が、例え自身との私的な関係に由来しているとしても、それが裕一郎が職場を去る理由に重なると、高志が考えるのは奇妙ではある。裕一郎が、自分の撤退と亜希のことが関連しているだろうなと自覚するのも同様だ。 何故だろう。その奇妙をむしろ当然だと思ってしまう六十近い男が二人、若い娘が遺して行ったある鮮やかさに支配されて向かい合っていた。 「秋に松下君が辞める前、逢うたんか? 何か言うてたか?」 「いや。現場帰りに呑んだけど何も言うてなかったぞ。なんで?」 「そうか。そんな気がしたんや」 高志のデスクと社員のデスク群との間の壁面に、コルクボードがあって、様々な連絡事項が貼られている。資格試験の講習会、新入社員歓迎会・・・。隅に絵葉書がピン止めされている。松下さんより!と矢印を描いた紙が横に貼ってあった。 「見てもええかな?」 「ああ・・・。辞めた直後、チーム宛に来たらしい。何ヶ月にもなるのに、連中が外し忘れとるんや。瀬戸内海の写真やな、消印は下関や。携帯電話の番号もアドレスも変わっていて繋がらないらしい」 手に取って、絵写真の裏を見ると、宛名欄の下半分にチーム員四人のニックネームがあって、その一人一人への短い激励とアドバイスが書いてある。寝過しが貴方のホントの力量を半減させていると思う、現場に足を運べば今以上に人は動いてくれるはず、発注遅れは結果としてと言う以前に元々現場軽視なんです、連日事務所に遅くまで残っているのは決して誇るべきことではありません、などとあって、最後の行にこうあった。 私? 『ひと夜秘め独り往く朝霧あさし身捨つるほどの恋路はありや』 高志が「そんな気がしたんや」と言った根拠は分かっていたが、答えようもない。 「松下さん、誰かと別れたんか?」 「心当たりないな・・・。社員のプライベートは知らん」 「パロディと言うか、これ本歌取りやな。本歌作者は笑うてるやろうけど、これは相手を責めるというのではなく、精一杯、自分と相手両方と言うか、関係全体を相対化しようと真面目に振り返っているよな」 「・・・・・・」 「高志。得難い人が辞めたな」 「・・・・・・・。黒川さんを手伝うって? 二度ほど彼から焼物を買うたことがある。大変やぞ、あのジジイ」 「ああ分かってる。まぁ短期間やし、沖縄には迷惑やろうが、癒し?リフレッシュ?」 「裕一郎、大阪に帰ったら、戻って来てもええんやぞ。場所は用意する」 声を出さず、片頬だけ崩して返した。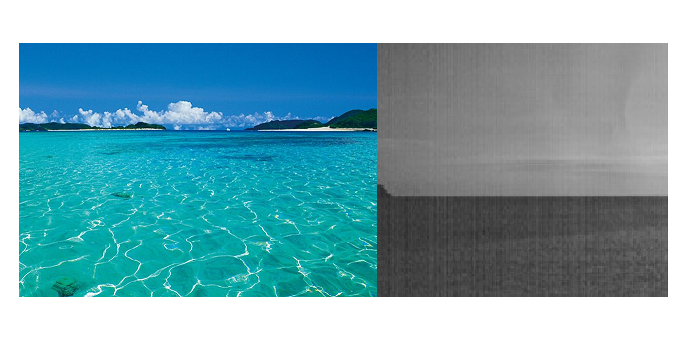
高志の背中の向こうのモノクロ映像には、墨絵薄闇の海と寄せて返す仄白い波が見える。映画の場面転換法ワイプのようにそれを追い出すカラー画面には、澄んで輝く空の下、緑の島とコバルト・ブルーの海が広がって行く。 噂を聞いていたからか、亜希が沖縄に居るような気がしていた。
(一章 チヂミ 終)
連載⑫: 『じねん 傘寿の祭り』 一. チヂミ (8)
一、 チヂミ ⑧
あれから二年と少し。今、亜希は若い男女社員四人を部下に持つチーム・リーダーとなっている。人が時として迷い込む不本意な些事に翻弄されることなどなく、きっと仕事にプライベートに二十代最後の充実した時間をテキパキと送っているだろうと思って来た。その後何度も仕事をしたが、呑むのはその時以来もう何度目だろう。その多くは現場関係の連中も居て二人ではなかったが・・・。現場でも呑む場でも「男前」を崩すことなど決してなかった亜希の迷路など思ってもみなかった。 最終電車前に合わせた閉店時間だ。最後まで騒いでいた文化祭打上げ組も帰った。レジに進もうとして、皿に数片残されたチヂミが目に入った。いつぞやは、亜希は残さず食べた。その夜より本場風で美味いチヂミだったが、チヂミ自身は残されたことに納得しているように見える。 亜希を送って駅へ向かうと、駅前の広場にラーメンの屋台が出ている。 さっき黒川一家の送別会に最後にやって来た、教師だという若い夫婦が仲睦まじく木の長椅子に腰掛けてすすっていた。あの後、黒川節を延々と聞かされたのだろう。軽く会釈して過ぎた。 「キャリアの話ですけど、あれ、あの時は胸に沁みたんですよ、ほんとに・・・。けれど、最近の私、そんな感覚失ってるんです。仕事をこなしているだけみたいな、どうでもいいやみたいな」 「・・・・・・」 亜希、それはぼくのことだ、「こなしてるだけ」「どうでもいいや」。 「最近の私」は「最近の北嶋さん」と聞こえて来るのだった。 「北嶋さん。あの時のキャリアにひとつ大切な要素が抜けてません?」 「ん? 何」 「年齢! 残念ながら人間は歳を取るんです。これお互いですけど」 「・・・・・・残念ながらではなく、『幸いなことに』と開き直るしかないね」 そうは返したが、階段を上りながら思った、その通りだと。人が早くに識っている事柄に歳を重ねてから気付くというのは、単に不誠実な半生の証しでしかない、と。それがどんなキャリアになると言うのだ・・・。 券売機で亜希の切符を買った。
さっき黒川一家の送別会に最後にやって来た、教師だという若い夫婦が仲睦まじく木の長椅子に腰掛けてすすっていた。あの後、黒川節を延々と聞かされたのだろう。軽く会釈して過ぎた。 「キャリアの話ですけど、あれ、あの時は胸に沁みたんですよ、ほんとに・・・。けれど、最近の私、そんな感覚失ってるんです。仕事をこなしているだけみたいな、どうでもいいやみたいな」 「・・・・・・」 亜希、それはぼくのことだ、「こなしてるだけ」「どうでもいいや」。 「最近の私」は「最近の北嶋さん」と聞こえて来るのだった。 「北嶋さん。あの時のキャリアにひとつ大切な要素が抜けてません?」 「ん? 何」 「年齢! 残念ながら人間は歳を取るんです。これお互いですけど」 「・・・・・・残念ながらではなく、『幸いなことに』と開き直るしかないね」 そうは返したが、階段を上りながら思った、その通りだと。人が早くに識っている事柄に歳を重ねてから気付くというのは、単に不誠実な半生の証しでしかない、と。それがどんなキャリアになると言うのだ・・・。 券売機で亜希の切符を買った。
裕一郎は、改札口を越えるとき亜希が言った言葉を忘れられずに居る。 「北嶋さんにしといたらよかった。北嶋さん、独り身だし」 松下亜希。酔った女の戯言であっても、罪なことを言うてくれるなよ。それに俺は独り身じゃない。帰れないだけだ。 今夜三ヶ所で呑んだ亜希は、もう、ことの終りを宣言していたと思った。さっき、黒川一家の送別会でユウくんと言い合っていた「沖縄へ来てね」「行こうかな。泊めてくれる?」も案外本気かもしれない。 駅から独り住まいの自宅マンションへの、もう閉まっていて街灯も消えている商店街を歩きながら認めていた。さっき亜希と呑み始めてすぐに二人の関係に気付いたのではなく、元々知っていたのだと。 年初めの現場で、亜希から菓子を貰ったことがあった。現場の職人らとおやつに食べた。友人の結婚式に行って来たとのことだった。 翌日、別の場所で同じものを食べたのだ。高志と呑んで、「うちに来いや、呑み直そう。久しぶりやから玲子も喜ぶよ」と誘われ、深夜に訪ねた。起きていた玲子が「もう呑みすぎでしょう」と咎めたが、しばらく呑んだ後、亜希から貰ったものと同じ菓子が出て来たのだ。 「さあさあもうお終いや。これ、高志が業界の一泊ゴルフ旅行で貰って来たんよ、案外美味しいよ。タルト言うんよ。甘いもの食べてお茶飲んで、二人とも明日も働かんと」 裕一郎は納得した。その時きっと自分は、瞬時に、二つの場所で出た同じ菓子を結び付けないことにしたのだと。 「この和風ロール・ケーキのどこがタルトやねん?」と酔った頭で思っていた記憶はある。
連載⑪: 『じねん 傘寿の祭り』 一、チヂミ (7)
一、チヂミ ⑦
「私、この仕事に向いてないみたい。キャリアもないし、思い違いや失敗ばっかり。北嶋さんにも迷惑かけてしまい申し訳ありません。仕事の成約に汲々として、成約したらしたで安心してしまい、押さえるべきいろんなことがしょっちゅう抜けてしまうんです」 裕一郎は、下心ゆえに、いやそうでもなかったのだが、キザなセリフで応えたのだ。自身が運営していた会社ではそうは出来なかったことを埋め合わせるかのように・・・。 「思い違いや失敗の数こそが、この仕事の蓄積、つまりキャリアです。もし、ぼくに、貴女より多く持っているものがあるとしたら、それは思い違いと失敗の数だけ。心配無用。松下さん、貴女は今日、確実にひとつのキャリアを積んだということです」 亜希の瞳が潤んでいるように見えた。まあ、よくも真顔でこんな歯の浮くセリフを吐けたものだと、我ながらこそばゆい。 亜希が声を落として言う。 「前の仕事では人間関係で躓くし、情けないです」 「躓きもしない人間関係なんぞ、人間関係じゃない。それはただの社交でしょ」 亜希が好物ですと注文したチヂミが皿に二片残っている。亜希はそれを二片とも食べ、声を元に戻して言った。 「・・・ハイ、もちろんそう思うことにしてます。」 「今の会社はええでしょう。外から見ていても、ぼくが会社経営で出来なかったことを出来ているように感じる」  「先月、同じフロアの隣の会社で自殺者が出たんです。うちはみんな、遅くなって深夜に社に戻ることも多いんですが、思い詰めた表情の彼に廊下やエレベーターで皆がよく出会いました。隣は、屋外広告から販促チラシまで幅広い広告媒体を扱う会社ですが、ムチャクチャきついノルマがあって、朝礼でミスが重なったり成績不振だったりするたった一人の人を日替わりで、全員で次々に罵り責める声が聞こえて来たりするんです。死んだ人はしょっちゅうだったそうです。ある時なんか、女性幹部が『この無能野郎!お前の言い訳は小学生以下の自己責任回避症だ。明日から小学校へ行って学び直せ!』と怒鳴る大声が、廊下にまで響いていました。震えるほど恐かったです。トイレで泣いていた彼を、うちの男性社員が直後に目撃してます。間違いなく追い詰められた自殺です。数日後の朝礼で専務が言ったんです。これは殺人だ。仕事に、命を絶たなければならないほどのことなんてない、絶対にない。追い詰められる前に、家族・友人・恋人・同僚・ぼくら、どこへでもぶちまけてくれ。それに耳を傾けられないような会社や組織に存在価値はない、って。どうか、ぼくら経営陣を殺人者にしないでくれ、って。」 「ふ~ん、吉田高志節やねえ」 「?。 いい会社に来たと思ってます。一~二年で前職に戻ろうと気軽に考えていた私の計画は、もちろん仕事を舐めてると言われて当然の構えですが、それよりもこの仕事が面白くなり始めていてヤバイです。友人が、前職に復帰してしかもそこにこの仕事を活かす道、というのが弁証法だと教えてくれました。」 「弁証法? 今でもそんな言葉を使うんや」
「先月、同じフロアの隣の会社で自殺者が出たんです。うちはみんな、遅くなって深夜に社に戻ることも多いんですが、思い詰めた表情の彼に廊下やエレベーターで皆がよく出会いました。隣は、屋外広告から販促チラシまで幅広い広告媒体を扱う会社ですが、ムチャクチャきついノルマがあって、朝礼でミスが重なったり成績不振だったりするたった一人の人を日替わりで、全員で次々に罵り責める声が聞こえて来たりするんです。死んだ人はしょっちゅうだったそうです。ある時なんか、女性幹部が『この無能野郎!お前の言い訳は小学生以下の自己責任回避症だ。明日から小学校へ行って学び直せ!』と怒鳴る大声が、廊下にまで響いていました。震えるほど恐かったです。トイレで泣いていた彼を、うちの男性社員が直後に目撃してます。間違いなく追い詰められた自殺です。数日後の朝礼で専務が言ったんです。これは殺人だ。仕事に、命を絶たなければならないほどのことなんてない、絶対にない。追い詰められる前に、家族・友人・恋人・同僚・ぼくら、どこへでもぶちまけてくれ。それに耳を傾けられないような会社や組織に存在価値はない、って。どうか、ぼくら経営陣を殺人者にしないでくれ、って。」 「ふ~ん、吉田高志節やねえ」 「?。 いい会社に来たと思ってます。一~二年で前職に戻ろうと気軽に考えていた私の計画は、もちろん仕事を舐めてると言われて当然の構えですが、それよりもこの仕事が面白くなり始めていてヤバイです。友人が、前職に復帰してしかもそこにこの仕事を活かす道、というのが弁証法だと教えてくれました。」 「弁証法? 今でもそんな言葉を使うんや」
連載⑩: 『じねん 傘寿の祭り』 一、 チヂミ (6)
一、 チヂミ ⑥
三年近く前、吉田高志の会社の下請ノザキに押し込んでもらって以来、亜希とは何度か組んで仕事をしたが、出会いから好感を抱いて来た。 仕事のスピード感や打てば響くような閃き、二十代にしては落ち着いた雰囲気、それとは逆に現状への違和感を湛えて遥か先を見ているような不安を宿した眼差し。 高志に「ノザキさんところに入った北嶋さんや」「偶然、学生時代の友人なんや」「顧問のようなもんや」「ヴェテランやから何でも相談したらええ」などと、今後仕事で関わりそうな一〇人近い若手中心の男女社員に紹介され、翌週の最初の案件が亜希が担当する現場だった。  当時、亜希は入社二年目になったばかり、前職は南アジア関係のNGO団体の仕事だったという。二年で辞めたそうだ。団体が関係するショップ開設で現場に出入りしていて、施工業者の高志の会社と出会い誘われて面白そうだと思い入社したという。前職を辞めた理由は聞けていないが、前職に戻りたいらしいという噂を他の社員から聞いていた。
当時、亜希は入社二年目になったばかり、前職は南アジア関係のNGO団体の仕事だったという。二年で辞めたそうだ。団体が関係するショップ開設で現場に出入りしていて、施工業者の高志の会社と出会い誘われて面白そうだと思い入社したという。前職を辞めた理由は聞けていないが、前職に戻りたいらしいという噂を他の社員から聞いていた。
数ヵ月後、暑い夏のある日、亜希と組んだ二つ目の現場で印象に残る出来事があった。亜希もそろそろ現場慣れして来ていた時期だ。その日も午後からもう冷房も稼動している現場に来て、シューズを履いてジーンズ・Tシャツの上に会社支給の夏用ブルゾンを羽織り、図面を手にあれこれとチェックに動いていた。職人の一人が「松下さん、えらい男前になったな」と言っていた。工事は無事終り、最後の清掃をしていた。裕一郎と亜希は、まずまずの仕上がりに満足している大工の棟梁や床工事の責任者などノザキ関係の人員も交えて、発注社長の到着を待って発注側担当者と談笑していた。 やって来た社長に別室に呼ばれた亜希がなかなか戻って来ない。嫌な予感がした。 数分後、亜希が沈んだ表情で出て来た。打合せや施工に不備があったのだろうか、別室で詰め寄られたようだ。やがて亜希はこちらへやって来て、泣き顔で言った。 「北嶋さん、すみません。出直しになりますけどやって下さい。メインの床材の品番が違ってました。どこかで、品番末尾の七と一を誤記したようです。サンプル現物を添えず、印刷カタログのカラー・コピーを切抜いて添えてた上に、その七と一はコピーでは色目的にほとんど同じで誰も気付かなかったようです。ゴメンナサイ。」 七には柄があり、一は無地だ。大いに違う。ダブル・チェックしておかないとこうなる。貼り替えは四十七㎡、安くはない。小さく短工期の現場ほど、この種の初歩的な失敗が起きやすいのだ。裕一郎にもこの種の失敗は山とある。今回、取り返しの付かない重大ミスではなかったのが不幸中の幸いだった。格安で貼り替えることとしたが、明後日には施主側手配の什器備品が搬入される。それの移動再設置には人手が要るので、緊急手配して明日中に完了しなければならない。裕一郎も早朝からの出動となるだろう。実費はそれなりに発生しても、ノザキと詰めた話をすれば、野崎氏は高志の会社との歴史と今後を考え丸く治めるに違いない。ミスはその範囲の軽傷だ。 帰路、落ち込む亜希を励まそうと現場に近いターミナル駅のガード下に誘ったのだった。
数分後、亜希が沈んだ表情で出て来た。打合せや施工に不備があったのだろうか、別室で詰め寄られたようだ。やがて亜希はこちらへやって来て、泣き顔で言った。 「北嶋さん、すみません。出直しになりますけどやって下さい。メインの床材の品番が違ってました。どこかで、品番末尾の七と一を誤記したようです。サンプル現物を添えず、印刷カタログのカラー・コピーを切抜いて添えてた上に、その七と一はコピーでは色目的にほとんど同じで誰も気付かなかったようです。ゴメンナサイ。」 七には柄があり、一は無地だ。大いに違う。ダブル・チェックしておかないとこうなる。貼り替えは四十七㎡、安くはない。小さく短工期の現場ほど、この種の初歩的な失敗が起きやすいのだ。裕一郎にもこの種の失敗は山とある。今回、取り返しの付かない重大ミスではなかったのが不幸中の幸いだった。格安で貼り替えることとしたが、明後日には施主側手配の什器備品が搬入される。それの移動再設置には人手が要るので、緊急手配して明日中に完了しなければならない。裕一郎も早朝からの出動となるだろう。実費はそれなりに発生しても、ノザキと詰めた話をすれば、野崎氏は高志の会社との歴史と今後を考え丸く治めるに違いない。ミスはその範囲の軽傷だ。 帰路、落ち込む亜希を励まそうと現場に近いターミナル駅のガード下に誘ったのだった。
連載⑨: 『じねん 傘寿の祭り』 一、 チヂミ (5)
一、チヂミ ⑤
「どんな理由で?」 「もう使命は終った。ここから先は経営に明確な価値を見出す経営者の哲学を持っているか、さもなくば労働組合の自主経営らしい違う働き方を構想し実践する思想を持つか、いずれかだ。そうでないとそれはケッタクソの延長だ、そのいずれも持ち得ていない以上解散しようと。」 「う~ん、難しいなぁ。で、労働組合はどうしたの?」 「高志は脱退して、独り他所へ行った。昔と同じように、散って闘う労働組合をいくつも作るんだと青いことを言ってたな。残った者七人で会社運営を続けたよ」 「それが、三年前に潰れた北嶋社長の会社、株式会社ワイ・トラップということですね?」 「そういうことや。その会社を二〇年強続けたが、経営者がぼくではアカンよな」 「その社名は吉田さんが居た頃からなの・・・? 社名の意味は?」 「高志の命名や。最初に支援してくれた会社の名の一部をもらったと聞いたけど・・・、社名は変更していない、引き継いだよ。」 「ふ~ん。で、専務吉田高志の紹介でうちの下請けのノザキへ・・・」 「そういうこと」 「あの人は、散っていくつも組合作ると言ってたプランを実際にしたの?」 「もちろん挑んだようやけど、一社目で一敗地にまみれ、あとは転々としたと聞いている。去るも地獄、残るも地獄と言うやろう。知ってるように、実際、派遣・請負・有期契約・パート、雇用の形が変えられ零細企業や下請けや非正規雇用の無権利状態のところにこそ組合は必要なんや。今はもっとそうや。」 「それを自己防衛から放置したのが日本の大手労働組合だとテレビで観ました。事態はその組合自身にも跳ね返って来ている、と」 「そうやな・・・。やがて、高志は、昔の取引先でもあるおたくの社長に呼ばれ専務稼業や。ぼくはぼくで、素人経営の辛酸を舐めた挙句、全てパア」
二つのエピソードを聞き終わり、生ビールをまた注文してググイッと飲み、チヂミを一片食べ、亜希は改まったように真顔で言った。 「北嶋さん、ありがとう。吉田高志という男の、知らなかった話も聞けました。高卒で工場へ行ったなんて知りませんでした。卒業を非難されたことへの意地の返答なんですか?」 「それは違うよ。意地でそんなことして何になる? 吉田に訊いたことがある。卒業を非難した人々の卒業をどう思うてると」 高志はどんな風に言ったのだったか。語り口調は思い出せないが、その趣旨は憶えている。 当時は今のように就職浪人や卒業後フリーターという状況ではなかった。その気さえあれば就職は出来たと思う。右肩上がり社会だった。卒業しないのも、卒業して高卒と詐称して工場へ行くのも、そういう70年代初頭の状況で可能な「贅沢な」選択のひとつだったんだ、と今の学生に言われたら、俺は「その通りや」と頷くよ。 自分の卒業を非難した人の多くがやがて卒業し、学生当時の言葉と行動からも「卒業」して行ったことは事実だ。 けれど、人々が、その卒業が生きて行く為に必要な条件の一つであるような現実を生きながら、なお「卒業」しない事柄を抱えて生きる限り、そして俺たちが、何事からも「卒業」しないような「愚かさ」からは「卒業」すべきだと自戒する限り、そこに軽重は無く、それぞれの数十年はいわば「等価」だ。例えば、お前と俺なら、どうであれそれぞれの理由で、仲間を離散させ仕事や職場を破綻させたのだ。 「あ~ぁ、も~うぉ。団塊オヤジがカッコ付けて。で、あなた方はいつ卒業するの? そんな風な一見冷静で思想的で文学的に聞こえる対応を、女とのことや家族には出来てないじゃないの。身勝手、優柔不断、建前、外づら、コソ泥、関係もドロドロ。男相手には無理して、一種の偽善です。」 「・・・・・・・」 「どうしようかな・・・。奥さんに逢おうかな? どう思う? 北嶋さんの意見は?」 「ぼくの意見と言うてもなぁ~・・・。もう結論出てるんでしょう?松下さんの中で・・・。それに、こうして男に言うのはちょっとどうかな、ぼくだって家族から斬られた身なんやし、参考意見なんか言えんよ。男やなくて女友達に聞いてもろたら?」 「女ねえ、居ませんよ話す相手。あの人と同世代のそれも男に聞きたいんです、あの世代の男は女々しいから・・・失礼・・・。女ならあの人の奥さんかな、話し合えそうに思う・・・。けど、こういう関係では無理だし」 高志の妻玲子が「逢おう」と言って来ている。逢ってもいいが、逢えば自分なりの言い分を展開するだろう。妻を傷付けるのもどうなのか? だから、もう捨て置け!という気分。高志が成り行きを自分で決めたらいいんだ。私に振るのはいただけない。そんなことだった。 「会社はどうするの? 難しいよな」 「なんで私が辞めなきゃならないんですか?」 「いや、辞めるべきとは言うてない。居り辛いやろうと・・・」 「だから、それはあの人も同じでしょ。私が辞めるってことを前提にするのって、北嶋さんらしくないよ。あ~ぁ、ガッカリだわ。こらっ! 団塊オヤジ!おいぼれ全共闘!」
 亜希は酔っていた。専務の永く古い友人とはいえ、そして六十前とはいえ、仮独り身の男の俺に気を許すな! 俺は貴女の輝きを視て来たんですよ。貴女の得がたい個性に魅かれて来たんですよ。崩れないでくれ・・・、裕一郎はそう思って、声を掛けた。 「こういうことも、ひとつのキャリアかもしれんな」 「キャリア?」 「いや、違うけどそんな面もあるかも、と。人生のキャリアと思えたらな、と」 「何がキャリアなもんですか。仕事みたいに行きませんもん。」 「それはそうやけど、だから、思えたらな、や」 「母親の轍は踏むまいと思って来たんです。今、進退窮まっている自分が情けなくて、それが悔しくて・・・」 「・・・・・・」 「憶えていますよ、北嶋さんが失敗の数がキャリアだって言ってくれたの・・・。」 「ぼくも憶えている。思い出しても恥ずかしい。」
亜希は酔っていた。専務の永く古い友人とはいえ、そして六十前とはいえ、仮独り身の男の俺に気を許すな! 俺は貴女の輝きを視て来たんですよ。貴女の得がたい個性に魅かれて来たんですよ。崩れないでくれ・・・、裕一郎はそう思って、声を掛けた。 「こういうことも、ひとつのキャリアかもしれんな」 「キャリア?」 「いや、違うけどそんな面もあるかも、と。人生のキャリアと思えたらな、と」 「何がキャリアなもんですか。仕事みたいに行きませんもん。」 「それはそうやけど、だから、思えたらな、や」 「母親の轍は踏むまいと思って来たんです。今、進退窮まっている自分が情けなくて、それが悔しくて・・・」 「・・・・・・」 「憶えていますよ、北嶋さんが失敗の数がキャリアだって言ってくれたの・・・。」 「ぼくも憶えている。思い出しても恥ずかしい。」
連載⑧: 『じねん 傘寿の祭り』 一、チヂミ (4)
一、チヂミ ④
総評って分かる? 労働組合というというものが、世直しへの大きな存在であり、そこでは排他的出世や能力主義という名の強いられた競争よりも、協働・共助の思想が生きている。ほとんど建前であっても、そんな神話が辛うじて生きていた最後の時代。それが、最後の総評なんやが・・・。 松下さんには信じられないよな、派遣・請負・パート等非正規雇用がいっぱいで、正規労働者の組合は知らん顔やもんな。当時、大阪の金属関係の労働組合は戦闘的で、吉田高志が居た会社でも永くもめていて、会社が希望退職を募り大混乱にあった。組合の説得努力にもかかわらず予想を超える希望退職者が出て、このこと自体が戦闘的と言われた労働組合とて例外ではない「神話の崩壊」の実例なんやけど、ともかく経営者の組合弱体化の目論みは功を奏し、生産ラインを維持できないほど「成果」が上がり、急遽求人するという無茶な労政だった。吉田高志は生産部門の職長で労組役員、その希望退職政策にはもちろんのこと、日頃の会社の労政にも激しく抵抗していた。 「だいたい話にはついて行ってますよ」 「君は聡明や」 「北嶋さんの、今のノザキでの雇用形態は?」 「ぼくは、ひとり親方、まぁ個人事業主かな、現場単位の請負やし。実際は老年フリーターやね」 「そうか・・・。で、あの人との再会はどんな風だったの?」 左翼用語かな?労働戦線・・・。 聞いて欲しいが、まぁ社会変革へのいろんな戦線があるとして、労働組合を中心に労働現場で行なうそれを労働戦線と言うたんやな、ぼくらは。ぼくは好きな言葉やないんやけどね・・・。その労働戦線へ、それも現業部門へ大卒を高卒と詐称して進んだ者は沢山いる。吉田高志が、さっき言った学生期最後の会話で言うた「もう逢えんやろな」は、そういうことやったんやと、そこで初めて知ったんや。まぁ、篠原玲子の部屋で聞かされた話には、ある一貫性があったということやな。ぼくは営業で入社したが、人員が育つまでとしばらく生産現場に居た。彼には、慣れない仕事を教えてもらった。労働組合や労働運動という知らない世界のことも教えてもらった。やがて、会社が金属什器製造販売から木製家具・店舗などの施工業へと守備範囲を広げて、ぼくも吉田高志も現在の仕事に至っているんや。 「さっきの、学生期と同じような彼の選択に遭遇したという話は?」
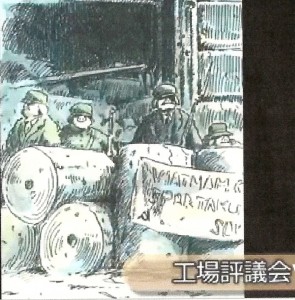 松下亜希は喰い付きよく聞いている。ときどきウンウンと頷いたりしている。三〇歳も違うこの女性に全て伝わっているとも思えなかったが、その頷きのタイミングは、よく理解できていますという者のそれだった。 「永い経過はあるけど、まぁ当事者だけに通じるローカルな話なんで、最後だけを言うよ」 「いいですよ、最後だけで」 会社は本格的に組合潰しに転じ、組合幹部は退社し、吉田高志が委員長になった。自分も組合役員となった。やがて、会社が雇った実力部隊との激しい攻防があり、それでも組合潰しを果たせなかった会社は、とうとう会社そのものを葬った。全員解雇・会社破産だ。 組合は、即刻職場を占拠して対抗、解雇撤回・企業再開をスローガンにバリケード封鎖して職場確保・占有権を主張。 「企業再開って、経営陣がもうヤ~メた!なら、そりゃ無理でしょう?」 「そうとばかりは言えん。まぁ方向性というかスローガンや。痛いところ突くねぇ」 実際は喰うや喰わず状態の中、バリケード占拠した社屋の中で会社を興し自主経営に挑んだ。吉田高志が社長だ。 五年間の職場占拠・自主経営を経て、解雇撤回・旧経営者の謝罪・解決金を得て、破産管財人と和解し職場を明け渡した。組合員は破産当初の十九名から八名になっていた。 「その時、組合解散・会社解散を強く提案した者がいた。その人物こそ、社長である吉田高志や」
松下亜希は喰い付きよく聞いている。ときどきウンウンと頷いたりしている。三〇歳も違うこの女性に全て伝わっているとも思えなかったが、その頷きのタイミングは、よく理解できていますという者のそれだった。 「永い経過はあるけど、まぁ当事者だけに通じるローカルな話なんで、最後だけを言うよ」 「いいですよ、最後だけで」 会社は本格的に組合潰しに転じ、組合幹部は退社し、吉田高志が委員長になった。自分も組合役員となった。やがて、会社が雇った実力部隊との激しい攻防があり、それでも組合潰しを果たせなかった会社は、とうとう会社そのものを葬った。全員解雇・会社破産だ。 組合は、即刻職場を占拠して対抗、解雇撤回・企業再開をスローガンにバリケード封鎖して職場確保・占有権を主張。 「企業再開って、経営陣がもうヤ~メた!なら、そりゃ無理でしょう?」 「そうとばかりは言えん。まぁ方向性というかスローガンや。痛いところ突くねぇ」 実際は喰うや喰わず状態の中、バリケード占拠した社屋の中で会社を興し自主経営に挑んだ。吉田高志が社長だ。 五年間の職場占拠・自主経営を経て、解雇撤回・旧経営者の謝罪・解決金を得て、破産管財人と和解し職場を明け渡した。組合員は破産当初の十九名から八名になっていた。 「その時、組合解散・会社解散を強く提案した者がいた。その人物こそ、社長である吉田高志や」
連載⑦: 『じねん 傘寿の祭り』 一、チヂミ (3)
一、チヂミ ③
ビールで酔ったわけでもないだろうが、突然、高志が歌を唄い出した。高志が唄うのを初めて聴いた。 『野に咲く花の、名前は知らな~い♪』 『戦さで死んだ、哀しい父さん♪』。時代の気分を漂わせていてちょっと投げやりで孤独な、だがひたむきな、そんな雰囲気が当時の若者に受けたのか、この歌の前のヒット曲で有名になっていたカルメン・マキという名の歌手の歌だ。聞いたこともある。だが、ぼくは、四番まであるその歌詞を諳んじているわけではない。ところが、高志はそれをたぶん正確に最後まで唄ったと思う。  「ええ歌やろう。清い女の子の軽い反戦歌やと思うか? これは深いでぇ」と言って、作詞者の短歌を無解説で紹介した。『マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや』(寺山修司) 彼もぼくも当時二十二歳。ぼくらは、いやぼくだけかも判らないが、短歌はもちろん表現世界のことには奥手だった。解らず語り、解らず聞いていた。 ただ、じっと聴いていた玲子の表情は、今も鮮明に覚えている。 「裕一郎、俺は大学を去るよ。お前とはもう逢えんやろな。まぁ、頑張ってくれ」最後にそう言った。大阪に所用があるという高志と、部屋をあとにしたのだが、そこで記憶は途切れている。 その後高志には逢っていなかった。言ってた通り卒業したと人から聞いた。玲子も消えた。ぼくは、学費を払わず大学を除籍になった。玲子の下宿部屋での一幕と野菜炒め、それが高志との学生期の最後の場面だ。もちろん玲子とも・・・。 数年後、高志と篠原玲子が結婚したとの噂を聞いた。その頃には、吉田高志を非難した人々の多くはもちろん卒業していた。
「ええ歌やろう。清い女の子の軽い反戦歌やと思うか? これは深いでぇ」と言って、作詞者の短歌を無解説で紹介した。『マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや』(寺山修司) 彼もぼくも当時二十二歳。ぼくらは、いやぼくだけかも判らないが、短歌はもちろん表現世界のことには奥手だった。解らず語り、解らず聞いていた。 ただ、じっと聴いていた玲子の表情は、今も鮮明に覚えている。 「裕一郎、俺は大学を去るよ。お前とはもう逢えんやろな。まぁ、頑張ってくれ」最後にそう言った。大阪に所用があるという高志と、部屋をあとにしたのだが、そこで記憶は途切れている。 その後高志には逢っていなかった。言ってた通り卒業したと人から聞いた。玲子も消えた。ぼくは、学費を払わず大学を除籍になった。玲子の下宿部屋での一幕と野菜炒め、それが高志との学生期の最後の場面だ。もちろん玲子とも・・・。 数年後、高志と篠原玲子が結婚したとの噂を聞いた。その頃には、吉田高志を非難した人々の多くはもちろん卒業していた。
「へぇ~、非難轟々の中でのリーダー格人物の選択ね、ふ~ん。あの人よりも、それを支えた玲子さん? 彼の奥さんに興味あるな」 「そうか?」 「そうですよ。想像だけど、熱くなってる学生には受け容れにくいんでしょ、そういう言い分って。で、北嶋さんは二人と再会するんですよね。やがて、三年前、ノザキへ紹介されるほどの仲になって行く、と」 「それはずっと後のことや。その前に同じ会社に居た。」 「えっ、それって初耳ですね」 「もう逢えんやろうな、と言った高志に偶然再会した。しかも再び彼の選択に遭遇したよ。」 一九七六年、失業中で職安、今のハロー・ワークに、背中に子を背負って通った挙句、適当な仕事がなくたまたま新聞の求人広告で入った会社、金属什器の製作会社に吉田高志が居た。お互い三十直前だった。 「背中に子供って?」 「女房が働いてくれてたんや」。亜希はククッと笑った。 「あの人、会社幹部になってたの?」 「いや、大学を卒業した彼が、そこでは高卒だった。製作現場に居て、労働組合の役員だった」 「高卒?」 「そう。選挙で外国の有名大学出身だと学歴詐称する奴もいるけど、この場合は別の意味ではあるけど、ひとつの学歴詐称や」 「北嶋さん、高卒だと学歴詐称してまで工場現場に居たあの人に、コムプレックス抱いたの?」 「それはないよ。その種の感情はないよ。本人も、奉仕や自己犠牲的というか清教徒みたいな見られ方は嫌やろう。」
当時の大学生に、天下国家や世の為人の為、かく生きるべき道などといった、明治以来知識人が社会に出る際に遭遇した葛藤があったとは思わない。大学進学率は六〇年代後半から急激に伸び、当時二十五%に達していた。所得倍増はほぼ成し遂げられ、戦後社会はピークの手前にあった。大学はすでに家電普及と同じ意味で大衆的普及現象のひとつだった。そこに学生叛乱期の深層が在るとぼくは思うんやが、それはともかく、いくらかの学生が知識人の責務などと悩んで進路選択したとしても、それを揶揄するつもりはない。吉田高志がその一人かどうか知らないが、そんな求道的と言うよりは欺瞞的な理由で工場現場へ行ったんやないと思う。現実的なというか技術的な理由やろう。そこに対してコムプレックスではぼくのポリシーに障るんや。 「技術的?」 「現業に行くには高卒が有効と言う技術的な話なんや」 「有効?」 「そうや、大卒が現業志望で来れば経営者は何か魂胆があるかもと疑うやろう」 「労働運動する為に工場へ行く・・・?」
連載⑥: 『じねん 傘寿の祭り』 一、チヂミ (2)
一、チヂミ ②
一九七〇年が明けた頃、二人が共に在籍していた大学の前年春から続く学内闘争は、その秋に機動隊が導入されバリケードは解除され、多数の逮捕者を出して混迷していた。 学生たちが、大学をバリケード封鎖した理由、つまりいくつかの要求とそれへの大学当局の拒否・無回答は、何ら変化していない。だから、大学の諸機能・諸スケジュールを今ここで認める訳には行かない、バリケードの有無に関係なく同じ対応をすべし、交渉に応じず勝ち誇ったように再開される大学側の運営は「粉砕」の対象だ、というのが闘争組織の共通認識だった。それにはもちろん「卒業試験」も含まれていた。 四年生高志は闘争組織のリーダー格で、その闘いの中心に居た。彼ら活動家は、大学という存在への、そして大学という存在からの、様々な問いと、その問いをも圧してしまう政治状況に向かうこととの間で、思考の分裂状態に在ったのだろうと思う。インテリ左翼の悩み? ぼくは、年齢は高志と同じだけど、九州や北海道で住込み店員など、まわり道をして大学へ来たので二年生だった。ノンポリって死語? 今選挙報道なんかで言われる無党派層と言うのとかなり違うと思うが、そのノンポリと闘争組織シンパの間を遊泳する二年生だった。大学生がストすることも含めて実はよく解らず、事態と自身の混乱に整理も付かず、身動き取れん状態で、自分には活動家の高尚な悩みなどなかった。 高志とは、入学年度は違うんだが、学内闘争が始まる前一時期倉庫の荷処理のバイトが同じで年齢も同じ、何故か気が合い「タメ口」で接していたよ。よく、大学から大阪へ出る途中にある繁華街で痛飲したりもしていた。
学生たちが、大学をバリケード封鎖した理由、つまりいくつかの要求とそれへの大学当局の拒否・無回答は、何ら変化していない。だから、大学の諸機能・諸スケジュールを今ここで認める訳には行かない、バリケードの有無に関係なく同じ対応をすべし、交渉に応じず勝ち誇ったように再開される大学側の運営は「粉砕」の対象だ、というのが闘争組織の共通認識だった。それにはもちろん「卒業試験」も含まれていた。 四年生高志は闘争組織のリーダー格で、その闘いの中心に居た。彼ら活動家は、大学という存在への、そして大学という存在からの、様々な問いと、その問いをも圧してしまう政治状況に向かうこととの間で、思考の分裂状態に在ったのだろうと思う。インテリ左翼の悩み? ぼくは、年齢は高志と同じだけど、九州や北海道で住込み店員など、まわり道をして大学へ来たので二年生だった。ノンポリって死語? 今選挙報道なんかで言われる無党派層と言うのとかなり違うと思うが、そのノンポリと闘争組織シンパの間を遊泳する二年生だった。大学生がストすることも含めて実はよく解らず、事態と自身の混乱に整理も付かず、身動き取れん状態で、自分には活動家の高尚な悩みなどなかった。 高志とは、入学年度は違うんだが、学内闘争が始まる前一時期倉庫の荷処理のバイトが同じで年齢も同じ、何故か気が合い「タメ口」で接していたよ。よく、大学から大阪へ出る途中にある繁華街で痛飲したりもしていた。
寒い夕刻、大学前駅で、同級で唯一の女友達である篠原玲子にバッタリ出会い声を掛けると、ほとんど同時に高志が後ろから声を掛けてきた。どうやら二人は待ち合わせていたようだった。 腹が減っていたからか、店に行くには金が無かったからか、三人で玲子の下宿部屋へ行った。途中で買ったビールを飲んで、玲子が学生下宿の共同炊事場で作ったおにぎりと野菜炒めを喰った記憶がある。当時の学生は個人の冷蔵庫などもちろん持ってはいなかったので、材料もその時買った豚肉とキャベツに、玲子の部屋の在り合わせの玉葱やニンジンなどだけなのだが、その野菜炒めがすこぶる美味かったのを憶えている。 しばらく雑談した後、高志は何と、近く実施される卒業試験を受けると切り出したのだ。 「四年生は卒業すればええんや。百人が百の職場や各種団体へ行けば、闘う労働組合や闘う団体が百できる。」と言い、話を続けた。 大学という特権地帯で、外には通用しない喧嘩を巡って「卒業試験をさせない」「受けない」ということに普遍的意味があるか? なら、大学側が態度を変えない限り永遠に卒業しないさせないのか? そういう問題の立て方は、いわば敵殲滅か味方玉砕かという、どこかで聞いた発想や、と。 「みんなから批判されていることも知っている。けど、俺は卒業するよ。苦労して兄弟の中で俺だけを大学へ行かせてくれた年老いた信州のお袋に、卒業証書見せたいからとでもしといてくれ。裕一郎、お前なら解ってくれるやろ?」 「お前なら」と言われて困惑したが、頷いたと思う。自分は、入学以来ただの一単位も取得していないし、卒業にも何のこだわりもない。だが、卒業を前提に大学生活を送り、最後の段階で卒業試験をボイコットする苦渋の選択をした多くの四年生がいることも知っている。リーダー格の学内著名人吉田高志の選択は非難されるだろうと思うと笑顔では聞けなかった。高志が「四年生は卒業すべし」と内部でキチンと意見表明しただろうかと気になったが、ぼくはそこを質すことも出来ずに居た。 残り少ない野菜炒めを惜しんでいると、玲子が自分の皿のものを半分移し寄越して「お腹空いてるんでしょ。ほら、これ食べて。私は昼遅かったから」と言った。有り難かった。
連載⑤: 『じねん 傘寿の祭り』 一、チヂミ (1)
一、 チヂミ ①
黒川一家の送別会を終えて駅に向かう道で、松下亜希が「もう少し呑みません?」と言った。亜希の方から誘われたことなどそれまでにはなかった。悪い気がするはずもない。その日は現場帰りと黒川家送別会に続き三軒目ということになる。裕一郎は、何か今日話したいことでもあるのだろうとも思ったが、男なら「俺と呑みたいのだ」と思いたい。そう思うと、亜希が黒川家までは大きな仕事バッグの手提げ部分にひっかけていた衣類を、今は着ていることに気付いた。濃紺のシャツの上に着た、現場着としても不自然ではないブラウン色のタイトなベストが高級品のように見えて来る。パンツ姿に、あれ、意外に背が高いなと足元を見ると、今日はヒール付の履物だった。こんな観察さえ男は出来ていない。
酒は進んだが、裕一郎は酔えなかった。黒川家近くの駅前にもある全国居酒屋チェーン店は、一〇時を過ぎても、多くの客が居て若いグループが騒いでいた。近くの大学の文化祭の日らしく、何かのサークルの打上げでしょ、と亜希が言った。店内には、その騒音の合間に、昔裕一郎が学生だったころ透き通った高音でファンを魅了した女性歌手の息子が、裏声を駆使して唄う歌が途切れ途切れて聞こえる。酔えなかったのは、若いグループの騒がしさだけが理由ではなかった。 専務との印象深い思い出?どんな青年だった?奥さんはどんな人?  何故松下亜希が、勤務する会社の専務でありその人となりも知っていよう高志のことを、あれこれ訊くのかと自問しながら、周りの雑音と息子歌手の裏声に馴染めず、母親の方が上手いな、などとぼんやり思っていた。やがて、ぼんやりを切り替え、すぐに、亜希は高志と男女の関係なのだと確信した。そう思ってしまった理由があるはずだが、その時は思い出せなかった。いや、思い出すことを避けたのだと思う。その心の揺れを隠すように、亜希が注文したチヂミに手を伸ばし、「これもらうよ」とつまんで、最初に亜希と呑んだ夜も彼女がチヂミを注文したことを思い出していた。 視線を亜希の手許のジョッキに固定して、ごく短い心の軌跡を見破られまいとして、流れている歌も耳に入る状態:「ぼんやり」に戻していた。あの女性歌手の息子が大人になり歌手となって、今唄っている。俺の息子もそんな年代なのだ、こっちは年寄りのはずだ。些細なことがきっかけで家を出て久しい。離婚したわけでも、離婚を巡って争っているのでもない。帰れないのだ。ふと溜息をついてしまった。 「北嶋さん、専務と昔からの友人だから?」 「えっ?何が」 「聞きたくないみたいだから」 「そんなことないよ、ちゃんと聞いてるよ」 「専務が言ったんですよ、ぼくのことは北嶋が一番知ってるって。聞かせて、あの人の青年時代」 高志からは、何も聞いていなかった。高志が亜希と特別な関係にあるということ、亜希が高志の妻のことを訊きたい心境に在ること。高志が重い荷物の何分の一かを自分に持たせようとしていること。 自分が、亜希のことを憎からず想っていることを高志に見透かされているようで困惑したが、何故か自分に与えられた役割を受け容れていた。
何故松下亜希が、勤務する会社の専務でありその人となりも知っていよう高志のことを、あれこれ訊くのかと自問しながら、周りの雑音と息子歌手の裏声に馴染めず、母親の方が上手いな、などとぼんやり思っていた。やがて、ぼんやりを切り替え、すぐに、亜希は高志と男女の関係なのだと確信した。そう思ってしまった理由があるはずだが、その時は思い出せなかった。いや、思い出すことを避けたのだと思う。その心の揺れを隠すように、亜希が注文したチヂミに手を伸ばし、「これもらうよ」とつまんで、最初に亜希と呑んだ夜も彼女がチヂミを注文したことを思い出していた。 視線を亜希の手許のジョッキに固定して、ごく短い心の軌跡を見破られまいとして、流れている歌も耳に入る状態:「ぼんやり」に戻していた。あの女性歌手の息子が大人になり歌手となって、今唄っている。俺の息子もそんな年代なのだ、こっちは年寄りのはずだ。些細なことがきっかけで家を出て久しい。離婚したわけでも、離婚を巡って争っているのでもない。帰れないのだ。ふと溜息をついてしまった。 「北嶋さん、専務と昔からの友人だから?」 「えっ?何が」 「聞きたくないみたいだから」 「そんなことないよ、ちゃんと聞いてるよ」 「専務が言ったんですよ、ぼくのことは北嶋が一番知ってるって。聞かせて、あの人の青年時代」 高志からは、何も聞いていなかった。高志が亜希と特別な関係にあるということ、亜希が高志の妻のことを訊きたい心境に在ること。高志が重い荷物の何分の一かを自分に持たせようとしていること。 自分が、亜希のことを憎からず想っていることを高志に見透かされているようで困惑したが、何故か自分に与えられた役割を受け容れていた。
「へえ~っ、そういう仲なんだ。そりゃ親友・戦友ですよね」 「どうかな、何やろうか・・・。お互いこいつにだけは信頼されていたいと思って来たような関係とでも言うのか、一番のライバルと言うのか、いつもよく似たテーマによく似た向かい方で関わって来たような感じかな。解り易く言えば同じ女を好きになるようなことかな」 「えーっ! あの人の奥さんを取り合ったんですか?」 「まさか! 違うよ、例えばや。解り易く言えば・・・と言うてるやないか」 裕一郎が、亜希に応えて話した「高志との印象深い思い出」「どんな青年だったか」は、高志との二つのエピソードだった。
連載④: 『じねん 傘寿の祭り』 プロローグ (4)
プロローグ(終)
「そりゃあ従兄弟だって、不景気の中、女房や従業員への遠慮もあるさ。昔、まだ従兄弟が小校生だったころ、百貨店勤めしていたあいつに、叔父夫婦が旅館を手伝ってくれって何度も頼んだのを断ったくせに」 「従兄弟さん夫婦は良くしてくれると言うてはりましたよ」 「そうかい?怪しいもんだ。あの歳で今更幹部でもないだろう。旅館の中枢なんて出来っこない。厄介者に決まってるじゃないか。何を意地を張ってるんだか・・・。君はひろしを置いて去るような女の言い分が解るのかね? 同じ団塊世代でも解らんだろう?」 「いえ、それはお二人のことですし」 「二人? 何を言っとるのかね。三人だよ、三人。ひろしが居なきゃぼくだって遠の昔にあいつと別れていたんだ」 「とにかく、黒川さんを手伝うことになったと・・・。もし、奥さんの思惑との間に摩擦が生じるのなら、ぼくは辞退しようと・・・」 「いいじゃないか、摩擦が生じても」 「いえ、どちらがどうということやなく、ぼくが来ることが何かを邪魔することになるのは辛いということです」 「で、摩擦が生じるのかね」 「いえ、どうぞ行ってやって下さいと言うてはりました」 「何を生意気な。棄てた者に何を言う資格もないんだよ。もうそれ以上言わなくていい。詳しい話を聞く気はないからね。君もそのつもりであいつの話はしないでくれ。特にひろしの前では一切ご法度だ。いいね」 黒川の不機嫌な表情が急に融けて和んだので、前に目をやると、そこに「ビジネス」の拠点=黒川宅の門があった。黒川が顎で家を指して言う。 「ここだよ。どうだい、デカイだろう。遠慮は要らん。今夜からは君の家でもあるんだ。自由にしなさい」 来てくれと懇願したことなど何処吹く風、書生相手に住まわせてやるぞと言っている政治家か文豪のような態度なのだ。家はもちろん借家だ。
 案内された二階の部屋は十畳の洋間で、大きなベッドが窓際に鎮座している。荷を解いていると、新品に見えるシャツに着替え、半ズボンを長ズボンに穿き替えたユウくんがやって来た。 「北嶋さん、お風呂?ごはん?」 「どっちでもええよ。ユウくんは?」 「ごはーん。今日は北嶋さんのカンケイ会だからチチが食堂へ行こうって。」 「へーえ、そうなんや。ありがとう」 階下へ下りると、黒川も着替えて玄関の鏡の前にいた。上着を着て、ネクタイを締め、髪もしっかり整えている。何や、ごはんが先と決まっていたんやないか! 「さあ行こう」「北嶋さん、早く早く」「何が食べたい?」 重なる二人の声を聞き分けながら、昨日松山で美枝子が言った「黒川が何を吹聴しても、世間様からひろしを棄てた母だと言われてもいいんです。」という言葉を思い出していた。 卒業式に向かう少年とそれを微笑んで眺める若い父親のように、颯爽として玄関を出る二人に続いた。 振り返えって、扉に鍵をかける黒川の背中を見ていると、扉の向こう側にここには居ないある人を閉じ込めて出かけるような気がした。四月那覇の夜風が生暖かい。上着が重い。
案内された二階の部屋は十畳の洋間で、大きなベッドが窓際に鎮座している。荷を解いていると、新品に見えるシャツに着替え、半ズボンを長ズボンに穿き替えたユウくんがやって来た。 「北嶋さん、お風呂?ごはん?」 「どっちでもええよ。ユウくんは?」 「ごはーん。今日は北嶋さんのカンケイ会だからチチが食堂へ行こうって。」 「へーえ、そうなんや。ありがとう」 階下へ下りると、黒川も着替えて玄関の鏡の前にいた。上着を着て、ネクタイを締め、髪もしっかり整えている。何や、ごはんが先と決まっていたんやないか! 「さあ行こう」「北嶋さん、早く早く」「何が食べたい?」 重なる二人の声を聞き分けながら、昨日松山で美枝子が言った「黒川が何を吹聴しても、世間様からひろしを棄てた母だと言われてもいいんです。」という言葉を思い出していた。 卒業式に向かう少年とそれを微笑んで眺める若い父親のように、颯爽として玄関を出る二人に続いた。 振り返えって、扉に鍵をかける黒川の背中を見ていると、扉の向こう側にここには居ないある人を閉じ込めて出かけるような気がした。四月那覇の夜風が生暖かい。上着が重い。
(プロローグ:終)